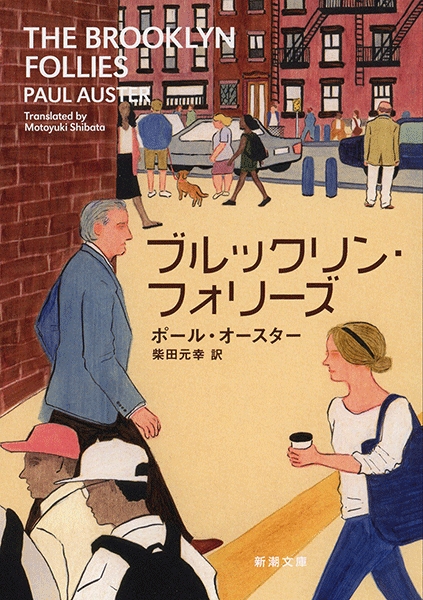
ポール・オースター「ブルックリン・フォリーズ」を読みました。いつものごとく、ディケンズ的な主人公による人生の立て直しの物語。彼の作品の中では、完成度が高いとはいえない、雑多な詰込みの作品ではないかと、最初は思いました。
でも今作は、若い世代を見守る中年男性の視点で描かれたがゆえに、非常につらい現実を語りながら、よりユーモアも感じられました。様々な理由で社会と折り合いをつけることができない人々を見守ってくれているような。ポール・オースターのあたたかい眼差しをより強く感じる作品。
では、いつものように、二人の精神科医の対話という形で、この後の感想を綴っていきます。刊行から時間が経った作品ですが、明確なネタバレもあるので、知らずに読みたい方はご注意下さい。
「我々はみな、最終的に巨大な力の前に敗れ去るけれど、それでも生きて、為すべきことがある。誰かのためでもあるし、自分のためでもある。それらは決して無駄じゃない。僕はポール・オースター「ブルックリン・フォリーズ」を読んで、そんな感想を抱きました。」
西山大介はわずかの間、中空を見つめた。彼が物語を要約するときの手順だ。
「なんだか、「かえるくん、東京を救う」(「神の子どもたちはみな踊る」収録)で、かえるくんが主人公に語る内容に似てますね。」
遠藤凪は、ポール・オースターというアメリカの作家について大介に尋ねていた。
「うん。物語の構造自体、村上春樹に似ています。自分はいったい何者なのか?という問いに、いくつもの伏線、いくつもの謎が絡み、それが交差し収斂していく。社会から孤立した人々、マイノリティーの物語。」
「翻訳者も村上さんの友だち、柴田元幸だからか。村上春樹が好きでアメリカ文学を読みたいなら、まず最初に、といった感じで、よく紹介されてますよね。小川洋子が、リアリティのある枠組みの中で、ものすごく幻想的な話が繰広げられていく、と評して絶賛しているので読んでみたいなと。」
「小川さんが勧める「ムーン・パレス」は鉄板で面白いと思いますし、初期の作品は傑作が多いのでしょうが、どこか割り切れない、うまく呑み込めない何かが胸に残ります。少なくとも僕はそうでした。」
「図書館や三洋堂の100円コーナーで拾って読む分には十分すぎる傑作だけども?」
凪はクスクス笑う。新刊の翻訳書は図書館で、は西山の口癖だ。
「からかわないで。「ブルックリン・フォリーズ」を勧めるのは、初期のように幻想的な話ではない代わりに、なんだか、ほっとするんです。
最初、人物説明が多くてとっつきにくいけど、語り手のネイサンと、その甥トム。トムが働く古書店の店主ハリー、トムの行方知らずの妹オーロラ。彼らの人間関係を理解すると俄然面白くなってきます。従来のミステリー要素もあるし、LGBTQ2+を主とするマイノリティーの人々へ寄り添う視点、そして家庭内暴力や児童虐待、宗教、マインド・コントロールについても掘り下げています。」
「村上春樹的ということは、心理療法にまつわる物語、あるいは、物語を語ることはすなわち心理療法であるという分析もできそうな感じ?」
「そうですね。行方不明のオーロラの娘で、9歳になる少女ルーシーが突然ネイサンを訪ねてきて、しかも緘黙で何もしゃべらないんです。のちの説明から自閉スペクトラム症ないし、虐待の影響ではないかと推測できるんですが。
困惑したネイサンは甥のトムと相談して、意地悪かもしれないけど、自分たちと違って一応家庭があるおばさんに預けようと、遠路はるばる旅をする。そうやって物語が動き出す。そのドライブの途中で、文学研究者だったトムは、フランツ・カフカが人形を無くした少女に手紙を送る話をします。」
「カフカのその話は知ってます。人形は自分探しの旅に出たという話を捏造するんですよね。カフカは手紙を重ねながら、人形の通う学校、新しく知り合う人々といった細部を描写する。だんだん人形の人生は複雑になっていく。どうやら女の子の元に帰れそうもない。手紙は語る。」
「そう。最終的にカフカは、人形が結婚して幸せに暮らしていることにします。美しい、説得力ある嘘を思いつければ、女の子の喪失を、違う現実にすり替えることができるのだから。(P225) 旅の途中、意地悪なおばさんの所にやられるのが嫌なルーシーは、砂糖をガソリン・タンクに詰め込んで、車を故障させてしまいます。そのことを後で知ったネイサンは、ルーシーを叱ろうとして、思いとどまります。
一瞬、混じり気なしのショックに私は襲われ、それから、怒りの波が体を貫くのを感じるが、ひとたび波が過ぎると、怒りの感情はなくなっている。怒りが同情に代わり、私は悟る。ここで彼女を叱ったら、私は彼女の信頼を永久に失ってしまうだろう。(P290)
車を壊されたことは大変迷惑だし、腹が立つ。けれども、それよりも、虐待された9歳の少女が、おじさんを頼ったのに、意地悪なおばさんの所にやられてしまう。それこそ9歳の少女にとって、非常に過酷な状況なんです。」
「絵本「すてきな三にんぐみ」を思い出しました。怖い盗賊3人組がある日襲った馬車には、みなしごのティファニーちゃんしかおらず。彼らはティファニーを連れ帰る。彼女は意地悪なおばさんの所にやられるはずだったので、このおじさんたちのほうがなんだか楽しそう。」
遠藤凪の瞳がキラキラする。絵本の中の女の子を思い浮かべているのか。
「すてきな三にんぐみはみなしごを集めた町を作るんでしたね。さて、物語の後半、ネイサンは、数少ないヒントを頼りに、姪のオーロラの居場所を突き止めます。カルト宗教の狂信者である夫に幽閉されていた彼女は、やっとのことで娘のルーシーだけ逃げのびさせたのでした。彼女を救いに来たネイサンにオーロラは長い物語を語ります。
弱さのせいで自分を主張できなくて、臆病だから反抗することもできなかった。相手が自分より優れていると思ってしまうとそうなるのよね。自分で考えるのをやめてしまって、あっという間に自分の人生が自分のものでなくなる。しかもそのことに気づきもしない。(P381)
人は自分に対する力を譲り渡しちゃいけない。たとえ相手の人格を信じていても、たとえ、相手が一番物事をわかっているんだと思っていても。(P384)」
「カルト宗教によるマインド・コントロールと、依存、児童虐待は、対処しにくい問題ですね。一見すれば本人の意思で結婚したり従ったりしてるようにしか見えないから。」
「ええ。人生の岐路にあって、悩んでいる人に対して、勧誘する人は、最初はほめまくって、しだいに個人的問題を聞き出していく。
今まで親の言いなりで決めてきた。学校も仕事も。自分は変わらないといけないと考えている。そういった、実は、親兄弟との繋がりが希薄な人たちがターゲットになりやすい。「あなたは今、人生の転換期にある」といった殺し文句が背中をプッシュしてくる。」
「最初は意図を隠して誘うんですよね。実は宗教であることを隠す。教育によってしだいに認識を変えていき、自分で判断して入信したと思わせる。
誘いこまれたあとに宗教だと明かされるが、自分で選んだと信じ込んでいるから後戻りできない。人間は自分が決めた決定を、後で間違いだったとは思いたくないから。」
「「君は悪くない」、「何も考えなくていい」、「周りの人は悪い人だから、嘘をついてでも、こちら側に引き入れないといけない。」といった理屈を信じ込まされる。
外部との接触を禁じられ、友人や家族からも引き離される。社会的遮断 他人と相談できないから、誤った考えが修正されない。」
「明確な指示を与えられるから、ある意味、楽に思えるのもミソですね。都合よく労働させられたりしちゃう。その仕事の中で、うまくいったのは神のおかげ。うまくいかないのは自分が悪い。信心不足だから。そういわれると、ますます自分の頭で考えられなくなる。」
「よくできた宗教というものは、確かに人を救うかもしれない。悩みや苦しみを解決してくれるかもしれない。でも、裏を返せば、教義を絶対視して融通が利かなくなり、大切な人との絆を破壊する最悪なことだって起こり得る。
ロック・スター、プリンスが子どもを失った悲しみからエホバの証人に入信した際、音楽性が変化したのはこの際どうでもいい。エホバの証人の教義に従いすぎて、妻マイテに医学的治療を禁じてしまったエピソードは胸が苦しくなりました。」(マイテの回顧録「The Most Beautiful - プリンスと過ごした日々」P231、P243による)
「宗教はプリンスの苦悩に明解な説明を与え、彼の音楽的キャリアを復活させた。それは素晴らしいことだったけど、彼の妻をも救うことはできなかった。ブライアン・ウイルソンが薬物依存から抜け出せた反面...という話にも似てますね。」
「うん....。すべて都合よくうまくはいかないね。「ブルックリン・フォリーズ」の話に戻るけど、古書店の店主ハリーが亡くなったとき、彼に救われ、彼の下で働いていた青年ルーファスは、愛するハリーの葬儀の場に、ドラァグ・クイーンのティーナとして現れ、夜のお店で演じているパフォーマンスをします。愛するハリーを見送るために。」
その姿をネイサンはこう描写します。
彼は私がいままでに見た中で最高に美しい女性の一人だった。(中略)堂々たる未亡人の正装に身を包んだ彼は、絶対的な女らしさの権化に変身していた。その姿は、現実の女性の領域にある、いかなるものも超えた、女性的なるものの理念そのものだった。(中略)ティーナの威厳ある、痛ましい物腰は、悲しみに暮れる未亡人の完璧な表現であり、非凡な才能の女優によるパフォーマンスだった。(P328)
続いて。CDプレーヤーの音楽(「あの男を愛さずにいられない」)に合わせて口パクでパフォーマンスを始めたティーナについて。
それは堂々たる、かつ馬鹿げた、笑える、かつ胸のはり裂ける、感動的かつ、コミカルなパフォーマンスだった。それはそうしたものすべてであり、そうでないものすべてだった。(中略)私たちはそこに釘付けになって立ちつくし、彼女と一緒に泣くべきか、それとも笑うべきか、わからずにいた。(P329)
ハリーは遺言で、財産の半分をルーファス(ティーナ)に譲ると書いているのに、彼女は固辞して故郷へ帰ります。ニューヨークという大都会でつまはじきにされていたルーファスにとって、誇れるものはドラァグ・クイーンとしての自分と、愛するハリーだけだった。お金は要らない。関係ない。
マイテがプリンスと離婚する際、金銭を要求せず、結婚する前(ベリーダンサーとして稼いでいた)と比べたら、ほぼ無一文で故郷に帰ったという話と重なります。彼女はその後、結婚せずに養子をもらい、動物保護の活動をしています。(マイテの回顧録「The Most Beautiful - プリンスと過ごした日々」P254、P281他による)
ハリーの財産(希少なものを扱う古本屋)を山分けすることになったトムは、ルーファスを説得しようとします。この部分も、全然関連性はないけど、どうしてか、「すてきな三にんぐみ」を思い出します。先述のハリーの葬儀の前の話。
「半分ずつだよ。ルーファス。何もかも二人で分けるんだ」
「薬の金だけ送っておくれよ」ルーファスは小声で言った。「後は何もほしくない。」
(中略)「ここはあたいのいるところじゃないよ。本のことなんか何も知らないし。あたいはただのフリークだよ、しょせんよそ者の色つきのフリークだよ。男の子の体をした女の子、故郷が恋しい、死にかけている男の子だよ」
「君は死にはしないよ」とトムは言った。「君は健康だよ」
「あたしたちはみんな死ぬんだよベイビー」(P323)
黙って聞いていた遠藤凪が補足する。
「誇り高くて、寂しい.....。アノーニ&ザ・ジョンソンズやシルヴェスターの音楽を思い出します。」

Sylvester on stage in London in 1979
「うん。この物語は様々な人間模様が繰り広げられますが、私にとっては特にルーファスのエピソードが印象的でした。非常に音楽的で。」
「まとめると、カフカのお手紙による物語は、お人形を失った少女の心を自由にするために。カルトのマインド・コントロールは、人の心を束縛するために。そしてドラァグ・クイーンであることは、何物にも左右されず、自分が自分であるために、より高次の世界へ向かうこと、でしょうか。」
「彼女と一緒に泣くべきか、それとも笑うべきか、僕もわかりません。」


